開封率
- 配信したメールをユーザーが開いた割合のこと。
- 全体で平均すると大体20%程度になる。
- PCと比べるとスマホは開封率が高くなる。
- ユーザーの興味の直結する趣味系の内容は開封率が高くなる。
- 逆に、クーポン系のメルマガは開封率が低くなる。
クリック率
- 全体で平均すると2〜3%程度になる。
IPレピュテーションとは?
インターネット上のIPアドレスの信頼性をスコア化したもの。
送信元IPアドレス
専用IPアドレス(固定IPアドレス)
メリット
- メール大量送信時(年間10万件以上)にISPからの送信数の上限に引っかかりにくい。
- 自らIPレピュテーションのコントロールができて、他者の影響を受けない。
デメリット
- IPレピュテーションの維持管理にコストがかかる。
- IPレピュテーションを高めるまでの間に機会損失が発生する。
ユースケース
メルマガなど大量メール一括送信などをしたい場合など。
共有IPアドレス
メリット
- 同じIPアドレスの使用者が堅実なメール運用をしていれば、健全かつ豊富な送信実績からIPレピュテーションが高まっており、最初から到達率が高い状態でメール運用を開始できる。
- 固定IPに比べて取得運用のコストがかかる。
デメリット
- 他の使用者次第ではIPレピュテーションが低くなる可能性がある。
- スパムや迷惑だけでなく、バウンス率の上昇でIPレピュテーションが低下する可能性がある。
- ISPの送信数の制限を受けやすい。
ユースケース
一括送信などが必要なくとにかくコストを低く抑えたいケース。
IPウォームアップ
新しいIPアドレスで一気にメールを送ろうとするとスパムと疑われてしまう。新しいIPアドレスの場合は少しずつ配信量を増やすことでレピュテーションを上げる必要がある。
バウンスメールとは?
配信できなかったメールのこと。
ソフトバウンス
一時的な理由による配信エラーのこと。時間をおけば配信完了されることもあるし、受信者へ管理者から転送される場合もある。
原因
メールサイズが大きすぎる。
受信側のメールサーバーの規定で受信サイズが決まっている場合がある。
受信側のメールサーバがダウンしている。
何らかの理由でダウンしている。サーバーが復旧すれば再送されます。
受信者のメールボックスがいっぱいになっている。
メールボックスから不要メールを削除するか、メールボックスのサイズを拡張すれば再送される。
ハードバウンス
恒久的な理由による配信エラーのこと。
原因
メールアドレスに誤りがある。そもそも存在しない。
メールアドレスの利用者が退職して使われなくなったり、登録時に誤りがある場合などが考えられます。
受信側のメールサーバーのスパムメール、迷惑メールと疑われる。
フィルタリング機能があるメールサーバーもあります。
受信側のメーラーの振り分けで迷惑メールと判定される。
受信側のメーラーにも迷惑メールフィルタリング機能などがあります。
バウンスメールの対策
定期的にリストのメンテナンスをする。
例えば、メルマガを配信している場合などは定期的にバウンス率を確認して、不達の原因を確認する。
メールサイズが大きい
送信側ができるだけ軽くなるように意識する。
メアドに誤りがある。
登録フォームにチェック機能を実装する。
メールサーバーにスパムと判定されないようにする。
SPFやDKIMを使用する。
迷惑メールと判定されないようにする。
オプトイン、オプトアウトの見直しなどをする。


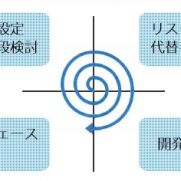

この記事へのコメントはありません。